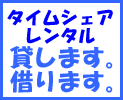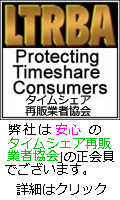タイムシェアハワイ
タイムシェアの4つの所有形態とは
2011年11月15日
名義をどのようにするか?多くの場合、夫婦や家族で所有する場合が多いので、悩む必要はないのですが、知らないと相続裁判で売却が難しくなったり、1人名義であっても、所有権のない配偶者までタイムシェアを売る時にサイン認証を行う必要があり注意が必要です。 それではまず4つの所有形態とはどのようなものか見て行きましょう。
| A:単独所有(Tenant in Severalty) |
個人が一人で、または法人が所有する場合の所有形態です。夫婦であっても、
夫または妻のどちらかの名義で所有する場合にはこれに該当いたします。ただし、
権利書には、所有権がなくとも配偶者の名前は表記されます。相続権は、
定められ法定相続人に帰属いたします。
ここがポイント!
・一人所有は死亡時に大変です。米国では1人所有の場合、死亡すると、相続する権利のある人を全て証明し、相続する人を裁判所で決める必要があります。これには費用と長引くと年単位の時間がかかるので注意が必要です。、多くの相続人はタイムシェアの売却を希望されますので、費用と時間を掛けてまで売却する価値がある物件かどうかまず、転売業者に確認されることが必要です。予め名義を家族名義にすることも相続裁判を避ける方法でもあります。ただ、名義を複数名にされる場合でも多額の費用が発生します。費用をかけるだけ価値があるタイムシェアであるかどうかも先に知っておく必要があります。
・法人で所有する場合 法人で所有する場合はタイムシェアリゾートに対して、代表者(法人の役員が条件)の名前を指定して登録してもらうことができます。登録されている人は、その人の名前で予約を行うことができますが、登録されていない方の名前では、予約することができません。これは不動産登記とは別で、あくまでも、そのリゾート内部での名義の登録です。購入時の段階で決めて頂く必要があります。
・ネバダ州(ラスベガス)のタイムシェアの登記については、夫婦のどちらかの名義で単独所有(Tenant in Severalty)であっても、将来、その物件を売却する場合には、権利書上には権利者として登記されていない配偶者もサイン認証をしないと、その物件の売却はできません。ラスベガスのタイムシェアを買って、結婚している息子も名義を入れる場合、息子の妻まで売却時にはサイン認証が必要となりますので安易な名義の登記は注意が必要です。
・一人所有は死亡時に大変です。米国では1人所有の場合、死亡すると、相続する権利のある人を全て証明し、相続する人を裁判所で決める必要があります。これには費用と長引くと年単位の時間がかかるので注意が必要です。、多くの相続人はタイムシェアの売却を希望されますので、費用と時間を掛けてまで売却する価値がある物件かどうかまず、転売業者に確認されることが必要です。予め名義を家族名義にすることも相続裁判を避ける方法でもあります。ただ、名義を複数名にされる場合でも多額の費用が発生します。費用をかけるだけ価値があるタイムシェアであるかどうかも先に知っておく必要があります。
・法人で所有する場合 法人で所有する場合はタイムシェアリゾートに対して、代表者(法人の役員が条件)の名前を指定して登録してもらうことができます。登録されている人は、その人の名前で予約を行うことができますが、登録されていない方の名前では、予約することができません。これは不動産登記とは別で、あくまでも、そのリゾート内部での名義の登録です。購入時の段階で決めて頂く必要があります。
・ネバダ州(ラスベガス)のタイムシェアの登記については、夫婦のどちらかの名義で単独所有(Tenant in Severalty)であっても、将来、その物件を売却する場合には、権利書上には権利者として登記されていない配偶者もサイン認証をしないと、その物件の売却はできません。ラスベガスのタイムシェアを買って、結婚している息子も名義を入れる場合、息子の妻まで売却時にはサイン認証が必要となりますので安易な名義の登記は注意が必要です。
| B:夫婦一体所有(Tenants by the Entirety) |
ネバダ州をのぞく州の物件には認められている所有形態で、夫婦が一体で所有する場合で、権利は不可分ですが、夫または妻のどちらかが、亡くなった場合にのみ、残った方にすべてのタイムシェアの所有権が移動して、上記AのTenant in Severaltyの所有形態となります。ネバダ州では、この所有形態は認められていませんので、夫婦で所有する場合には、下記のCまたはDのどちらかの形態になります。
ここがポイント!
ハワイ州のタイムシェアを夫婦で所有する場合はこの形態が一般的です。将来の相続がご不安な場合は子供も名義に入れてDの共同所有(Joint Tenants)にされるケースも多いです。
ハワイ州のタイムシェアを夫婦で所有する場合はこの形態が一般的です。将来の相続がご不安な場合は子供も名義に入れてDの共同所有(Joint Tenants)にされるケースも多いです。
| C:それぞれの持分を決めての共同所有(Tenants in Common) |
兄弟や友人などで、夫々の持分を違えて持ち合う所有の場合形態です。たとえば、兄は60%、弟は40%の権利で持ち合う場合は、この形態となります。相続権は、それぞれの法定相続人に帰属します。
ここがポイント!
持分の所有権が亡くなった所有者の相続人に行くことがポイントです。生存中の別の共同所有者には行きません。家族の場合は次のDのJoint Tenantsが一般的です。
持分の所有権が亡くなった所有者の相続人に行くことがポイントです。生存中の別の共同所有者には行きません。家族の場合は次のDのJoint Tenantsが一般的です。
| D:等分の持分での共同所有(Joint Tenants) |
両親と子供、兄弟、友人などが、等分の持分で所有する場合の形態です。Cの共同所有と違うところは、相続権は、共同所有している相手に当分に権利が移ります。たとえば、両親と子供2人の4人がこの形態で所有していて、父親が亡くなった場合には、父親の持分(1/4)の権利は、残った3人が当分に所有することとなります。
ここがポイント!
ハワイ州のタイムシェアに名義を登記できるためには、子供の年齢が18歳以上であることが必要です。
将来の相続のことも考えて子供の名義も入れるケースがございますが、売却時には仕事を休んで平日にサイン認証の必要があります。過去、1,100件以上のタイムシェアのご購入、ご売却に携わって感じたことですが、子供の名義を入れるかどうかの選択は、子供が積極的にタイムシェアを活用して海外旅行などをするタイプかどうかで判断いただくのがよろしいかと思います。
ハワイ州のタイムシェアに名義を登記できるためには、子供の年齢が18歳以上であることが必要です。
将来の相続のことも考えて子供の名義も入れるケースがございますが、売却時には仕事を休んで平日にサイン認証の必要があります。過去、1,100件以上のタイムシェアのご購入、ご売却に携わって感じたことですが、子供の名義を入れるかどうかの選択は、子供が積極的にタイムシェアを活用して海外旅行などをするタイプかどうかで判断いただくのがよろしいかと思います。
なお、どのような所有形態にしたら良いかについては、不動産会社は、お客様に直接アドバイスできる立場にはありません。法律に触れる分野ですので、お客様はご自身で判断されるか、もし疑問などがあったばあいには、専門分野の弁護士に相談していただく必要があります。
Copyright (C) 2002-2025 Timeshare Hawaii,Inc. All Rights Reserved